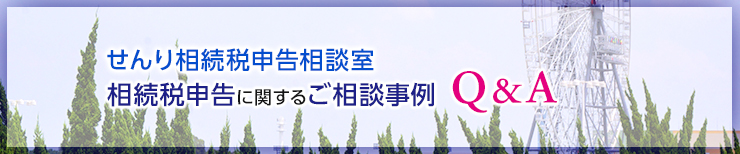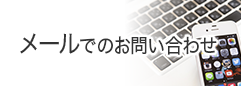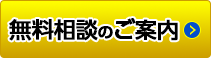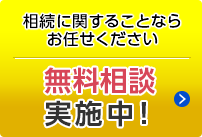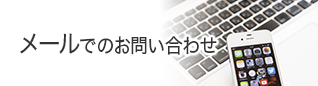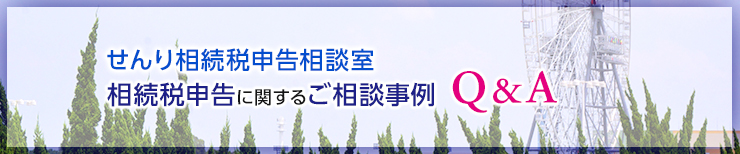
地域
2021年09月03日
Q:相続税申告は自分でできるものなのでしょうか。税理士の先生教えてください。(豊中)
先月末に長年連れ添った夫が亡くなりました。息子に手伝ってもらいながら葬儀を済ませ、遺品整理と相続手続きを進めようとしてます。息子に手伝ってもらいながら夫の管理していた口座や今暮らしている自宅、有価証券等、財産になりそうなものを計算してみたところ、相続税を支払わなくてはいけないということがわかりました。相続人は私と息子の2人になるかと思います。
私は私の両親の相続税手続きの際、専門家に依頼して済ませてしまいましたため、今回の夫の相続税手続きにおいても税理士など専門的な知識を持った人にお願いしてしまおうと思っていました。しかし、息子は専門家に依頼した場合、費用が余分にかかってしまうため自分たちでやってしまおうと言っています。
私も息子も働いており、あまり自由な時間は取れませんし、法律や税金に対する知識もありません。相続税申告をしたことがない、息子が自分で相続税申告を進めていくことはできるものなのでしょうか。(豊中)
A:ご自身で相続税の申告をすることは可能ですが、税理士に依頼する方が安心かつスムーズに進めることができます。
ご相談ありがとうございます。ご自身で相続税の手続きをすることは可能でございます。
しかし、知識のある専門家に依頼された方が安心であり、最も正確に進めてくれますのでお勧めです。
また、今回のようなケースですと財産に不動産や有価証券などが含まれており、より複雑な手続きを必要とするため、よくわからないまま申告してしまうことを防ぐことができます。もし、申告内容を間違えてしまった場合、過少申告加算税や延滞税といったペナルティが本来支払う税金に追加して課せられる可能性があります。そうなった場合、大切な財産を失うことになります。
相続税申告には期限が設けられていますため、その点にも注意をしてください。
どうしても豊中の皆さまがご自身で相続手続きを行う場合は、始める前に相続全体の流れを把握し、各申告期限なども十分に確認してから慎重に進めていってください。
もし、相続手続きや申告に対して少しでもご不安ある場合は、せんり相続税申告相談室の初回無料相談にお越しくださいませ。過去にご依頼いただいた案件のノウハウなど持ち得ていますため、お話を伺いながら税理士がサポートできることをお伝えさせていただきます。
豊中、豊中近郊のエリアに特化した税理士がご対応いたします。豊中の皆さまからのお問合せ、せんり相続税申告相談室スタッフ一同、心よりお待ちしております。
2021年08月04日
Q:相続税の申告に際し、実家の評価方法について司法書士の先生にアドバイスを頂きたい。(池田)
相続税の申告について司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。
池田の病院で闘病生活を送っていた父が、主治医のアドバイスもあり数カ月前から自宅に戻って私達家族と最後の時間を過ごしました。
残念ながら先日亡くなってしまったのですが、最期を家族と共に自宅で過ごせたことは本人にとって良かったのではないかと思っています。
相続人は、母と私の2人です。
財産調査を行ったところ、父の遺産は池田にある実家(一戸建て)と、預貯金が3000万円程度になります。
素人の私は実家の評価方法が分かりませんので、相続税申告が必要になるのかどうか現時点では見当もつきません。
できる限りお金をかけずに相続を済ませたく、相続税の申告のあるなしに関わらず自分でやろうと思っています。
そこで、実家の評価方法について教えて頂きたいのですが、素人にも分かり易く説明して頂けると有難いです。(池田)
A:少し難しくなりますが、相続税における建物の評価は固定資産税評価額、土地の評価は路線価で評価します。
相続税の申告における不動産評価は預貯金のように一目で見てわかるような金額があるわけではありませんので、法律により定められている方法により評価を行うことになります。
ご相談者様が相続する不動産はご自宅とのことですので、ご自宅の場合は土地と建物に分けて評価を行います。
土地の評価は、国税庁のホームページに掲載されている土地の時価を意味する“路線価”を用いて評価を行います。
この路線価を基に、対象となる土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して、評価額を下げることが可能となります。評価額が下がることで実際の納税額を下げる事が可能となります。
また、路線価の定められていない地域に関しては倍率方式という、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じる方法で計算をします。
建物に関しては、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書に記載される固定資産税評価額を確認します。
“価格”と記載されている箇所が固定資産税評価額になります。
なお、課税標準額とは異なります。
いずれにせよ、不動産を含む相続において相続税申告が必要となった場合は、専門的な知識を駆使して評価する必要があります。また相続税には申告期限もありますので、相続税の申告を専門とする税理士へ依頼される事をお勧めいたします。
せんり相続税申告相談室では、池田の地域事情に詳しい相続税申告の実績豊富な税理士が池田周辺にお住まいの皆様の頼れる相続税の専門家として相続開始から相続税申告までしっかりとサポートさせて頂いております。
初回のご相談は無料ですので、池田周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。
池田の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2021年07月03日
Q 税理士の先生に伺いたいのですが、生前に贈与された財産も相続税の対象になるのでしょうか?(箕面)
初めまして。箕面で暮らしている40代主婦です。生前贈与についてのご相談です。
私の父は持病が悪化し先日亡くなりました。父の持病が心配で私の家族が住む家で同居していたこともあり、子供の進学費用などの名目で何度か父から贈与を受けています。
年間の贈与額は110万円を超えていないため、贈与税の申告や納税はしていませんが、父の財産の相続税申告するにあたり、これまでに受け取ったお金はどのように扱えばよいのでしょうか。今のところ遺言書は見つかっておらず、相続人は私と兄の2名です。(箕面)
A お父様が亡くなった日から3年前までの贈与分を相続税に含めて計算してください。
結論から申しますと、相続税の計算では相続が開始された日から3年前までの贈与分については相続税の課税価格に含めて計算してください。
下記に記載した、この相続によって財産を取得する人が対象となります。
- 財産を取得した相続人
- 受遺者
- みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
- 相続時精算課税制度の適用者
上記に当てはまる人が被相続人から生前贈与を受けていた場合には贈与分を相続税の計算に含めて算出します。
したがって、今回の相続についてはお父様が亡くなる前の3年間でご相談者様が受け取った贈与分は課税価格に加算されることとなります。ご相談者様のお子様の贈与分については、生命保険等を受け取っているかによって異なってきますので確認が必要です。
また、課税価格に加算する必要がなくなる贈与税の特例もありますので、適用していたかどうかの確認が必要です。
相続税の課税価格の計算は上記のような制度を把握した上で行う必要があります。
どの財産が課税の対象となるのかは知識がないとご自身の判断では困難です。理解していない中でいい加減に計算を行い、本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、後々ペナルティを受けてしまう可能性もございますので注意しましょう。
被相続人の生前に贈与があった方は、まずは相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。当事務所では、箕面の皆様の相続税申告をお手伝いさせていただいております。
被相続人の最後の住所地が箕面の方、相続人の方が箕面にお住まいの場合など、箕面で相続税申告のご相談ならせんり相続税申告相談室へお気軽にご相談ください。
相続税に特化した専門家がご相談者様の相続税申告を丁寧にお手伝いさせていただきます。
初回のご相談は完全無料で対応させていただいておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
18 / 23«...10...1617181920...»
まずはお気軽にお電話ください
0120-765-745(予約専用ダイヤル)
営業時間:平日9:00~18:30(土は要予約)

堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。