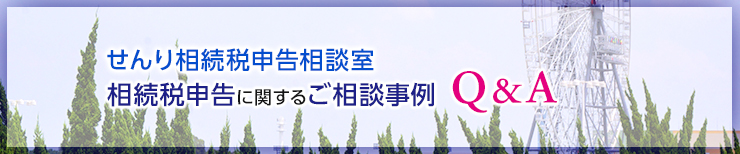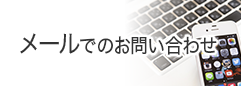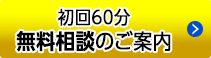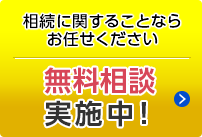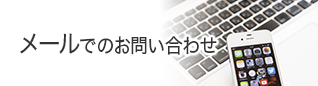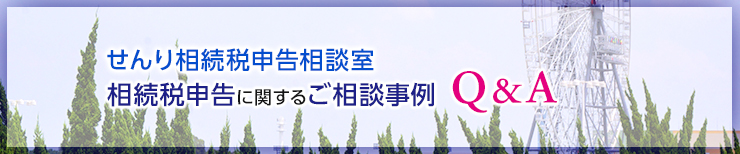
箕面市
2023年08月02日
Q:税理士に配偶者控除について伺います。(箕面)
数カ月前から病気の治療のため箕面市内の病院に入院している70代の夫について税理士の先生にお伺いしたいことがあります。医師の話によると夫の病状は芳しくなく、ある程度の覚悟を持って過ごしてほしいと言われました。私は今まで夫に頼って生きてきたため、夫がいなくなる人生なんて想像しただけでも不安で仕方ありません。とはいえ、私がしっかりした気持ちを持って今後の手続きなどをやらなければならないことは分かっているので、相続手続きなどについて私なりに調べています。我が家は自営業で、箕面には自宅と土地がいくつかあります。また、多少の貯えもあるのでもしかしたら相続税の支払いが必要になるかもしれません。不動産がいくつかある関係で税額が高額になることも考えられ、そうなるともしかしたら手持ちの現金だけでは相続税を支払えないかもしれません。調べていくにつれ配偶者には配偶者控除という相続税の減税に繋がる制度があるとわかったので、その制度について教えてください。(箕面)
A:配偶者控除で相続税の負担を抑えることができます。
ご主人様のご病状が芳しくない中、この先に起こるかもしれない「もしもの時」に備えて準備をされることは非常にお辛いこととお察しいたします。しかしながら、ご相談者様のように遺産に不動産が含まれる場合は相続税申告の可能性が高くなりますので、先に相続税の知識を得てから、可能な限り相続税の支払い額を減らせるよう準備されることは賢明かと思われます。
では、配偶者控除についてご説明いたします。相続税の配偶者控除は、亡くなった方の配偶者が負担する相続税の軽減を目的として設置されました。設置された背景としては、①被相続人の死亡後の配偶者の生活に配慮するため②被相続人の財産の維持形成には配偶者の貢献が不可欠だから③配偶者による財産の取得による次の相続への影響を考慮するため等が挙げられます。
具体的には、故人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、下記に挙げる条件のどちらかを満たしている場合に適用されます。
【相続税の配偶者控除】
①1億6千万円未満
②配偶者の法定相続分相当額
例えばご相談者様が実際に取得された遺産の総額が1億円だった場合には、①の1億6千万円以下となるため、相続税の課税はありません。ただし、その旨の報告をしなければ配偶者控除の適用はされませんので、必ず相続税申告をしましょう。
相続税の申告納税に関してご不安やご心配なことがある方は、相続税専門の税理士へご相談ください。
せんり相続税申告相談室では、箕面のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。せんり相続税申告相談室では箕面の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、せんり相続税申告相談室では箕面の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
箕面の皆様、ならびに箕面で相続税申告ができる税理士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2023年04月04日
Q:相続税の計算に死亡保険金は含めなければいけないのでしょうか。税理士の先生教えてください。(箕面)
箕面在住の50代男性です。先日箕面の実家に暮らしていた父が亡くなり相続が発生しましたので、母と協力して相続手続きを開始しました。相続人は母と私の2人だけで、相続財産は箕面の実家と預貯金が500万円ほどあるだけです。
相続税申告は不要だろうと思っていたのですが、どうやら父は生命保険に加入しており母は死亡保険金を受け取ったようです。もしこの死亡保険金が相続税の課税対象になるのであれば、相続税申告が必要になるかもしれません。死亡保険金は2000万円ほど受け取ったそうなのですが、この死亡保険金はどのように扱えばいいのでしょうか?(箕面)
A:契約内容によっては相続税の課税対象となりますので、契約書を確認しましょう。なお死亡保険金には非課税限度額が設けられています。
死亡保険金は、民法においては受取人固有の財産と見なされますので、相続財産には含まれません。よって遺産分割協議の対象にはなりませんが、税法上では「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となるので注意が必要です。
死亡保険金の契約者が誰なのか、受取人は誰になるかによって税金が異なってきます。まずはご相談者様の保険の契約内容について確認しましょう。
- 契約者と被保険者(被相続人)が同一人物で、相続人が受取人の場合:相続税
- 契約者と被保険者(被相続人)が異なり、契約者が受取人の場合:住民税、所得税
- 契約者と被保険者(被相続人)が異なり、受取人が第三者の場合:贈与税
死亡保険金の保険料を被相続人が全額もしくは一部を負担していたのであれば相続税の課税対象となりますが、死亡保険金には非課税限度額が設けられております。
この死亡保険金の非課税限度額は、法定相続人の数×500万円で算出され、この限度額を超えた分の金額が課税対象となります。
ご相談者様のケースですと、法定相続人はご相談者様とお母様のお2人ですので、非課税限度額は1,000万円(2人×500万=1,000万円)となります。したがって、受け取った2,000万円の死亡保険金のうち1,000万円が課税対象です。
なお補足ですが、死亡保険金を法定相続人以外の方が取得した場合は非課税の適用はされません。
このように被相続人が生命保険に加入していたのであれば、受け取った死亡保険金が相続税の課税対象になる可能性もあるので必ず確認しましょう。ご自身での判断がご心配であれば、相続税の専門家である税理士に相談されることをおすすめいたします。
せんり相続税申告相談室では相続税についての知識が豊富な税理士が、相続税についてお悩みを抱えている箕面の皆様のお力になります。初回のご相談は無料で承っておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。箕面の地域事情に詳しい税理士が、箕面の皆様ならびに箕面で相続税について相談できる事務所をお探しの皆様のお話を親身に伺い、全力でサポートさせていただきます。
2023年01月06日
Q:相続税の納税について質問です。配偶者が遺産を相続すれば税額が抑えられるのでしょうか。税理士の先生に相談したいです。(箕面)
税理士の先生に相続税の計算についてお伺いしたいことがあり問い合わせいたしました。
先日、長らく箕面で一緒に生活していた夫が亡くなりました。生活に関する手続きを夫に任せていた私は、相続税の税務に関しても詳しくありません。息子が2人いるので相続税申告についても任せるつもりでいましたが、遺産分割の際に息子たちと意見が分かれ困っています。
ありがたいことに、私は自分名義の財産を十分に所有しているので、夫の財産を受け取らなくても今後の生活に支障はありません。夫の財産には箕面の不動産も多く、管理が大変なため息子たち2人で遺産を分けてもらいたいと考えていました。
しかし、息子たちは相続税の関係上、私に財産を受け取ってほしいようなのです。配偶者である私が遺産を相続すると税額が安くなるというのが理由みたいですが、いまいち内容を理解していません。
配偶者である私が相続すれば、相続税額は抑えられるのでしょうか。税理士の先生にご相談させてください(箕面)
A:相続税には配偶者の税額軽減の制度がありますが、2次相続まで考慮して検討しましょう。
せんり相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
ご相談者様のご子息たちがおっしゃっているのは「配偶者の税額の軽減(配偶者控除)」のことかと思われます。被相続人の配偶者であれば、1億6千万円未満もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかからないという制度です。仮にご主人様の遺産から計算した課税価格の合計が1億円であったとしたら、ご相談者様が全てを相続すれば今回の相続において相続税の納税は不要となります。
配偶者控除は相続税額への影響が大きいため、「配偶者が遺産を多く引き継いだ方が得策では」と考えがちですが、大切なのは2次相続時の相続税についても考慮することです。
今回の相続でご相談者様がご主人様の遺産をすべて引き継いだ場合、ご相談者様の相続が発生した場合、ご子息たちが受け取る遺産の額が多くなることが想定されます。現状のまま2次相続がおこると、基礎控除額が少なくなるうえ配偶者控除は利用できません。今回の相続で遺産をご子息たちに分散させ、ご子息たちが相続税を支払っておいた方が、結果的に1次相続と2次相続をあわせた相続税の総額が少なくなる可能性もあるでしょう。
しかしながらこれらを正確に判断するためには、きちんと相続税の計算をし、2次相続時の納税額についてもシミュレーションする必要があります。相続税申告に関する知識がないと非常に難しい計算となりますので、ご主人さまの相続税申告も含め、ぜひ一度ご相談に起こしください。
せんり相続税申告相談室では箕面をはじめ、箕面付近の地域の皆様からも相続税申告に関するご依頼を承っております。箕面の皆様の相続税申告がスムーズに進むよう、申告が終わるまでしっかりとサポートをさせていただきますので、ぜひご相談にお越しください。初回相談は無料で対応させていただきます。箕面の皆様、ならびに箕面周辺にお住まいの皆様のご来所を心からお待ち申し上げております。
まずはお気軽にお電話ください
0120-765-745(予約専用ダイヤル)
営業時間 9:00~19:00(土曜日は要予約)

堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。